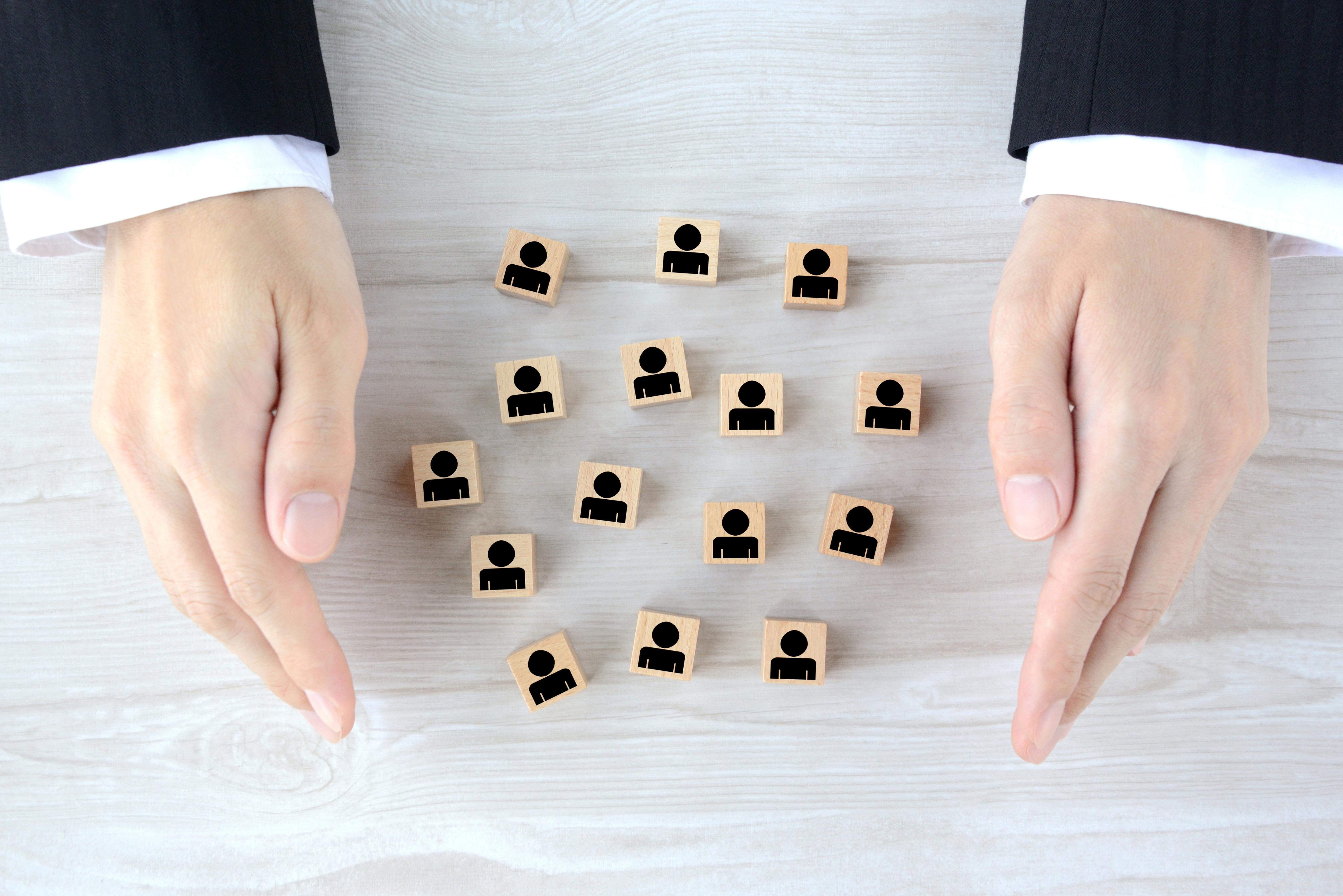
より良い環境を求めて転職する人も増えている一方で、入社したものの会社に馴染めなかったり、活躍ができなかったりして離職するケースも多く見られます。
採用した社員が退社してしまうと、新たに採用活動を行わなければならなくなったり、また教育をしなければならなくなったり、マイナス面も大きいので、なんとか定着率を上げたいと考えている企業も多いのではないでしょうか。
定着率を上げられるかどうかは、実は採用段階で大きく左右されると言っても過言ではありません。そこで今回は、人材の定着率が下がる要因と、定着率を向上させるための「適性検査」についてご紹介していきます。
1. 定着率とは
定着率とは、ある企業に就職した従業員が一定期間働いた後にどれだけ離職せずに残っているかを表す指標です。一方で、対になる指標として「離職率」があり、これは一定期間にどれくらいの従業員が離職したかを表しています。定着率が高い状態であるということは、離職率が低く組織の体制が安定していることになるので、企業経営において重要な指標のひとつです。逆にいえば、定着率が低い場合は離職率が高い状態にあるということになりますので、組織の体制に何らかの問題が生じている可能性が高いと考えられます。
定着率(%)は、「現在の在籍従業員数 ÷ 入社時の従業員数 × 100」で表されます。例えば、入社時の従業員数が100人で現在の在籍従業員が80人の場合、定着率80%といえます。
ただし、この計算方法においては、計測期間中(入社時〜現在の期間)に入社した人がいた場合は正確な値が算出できるとはいえません。
「(1年前の在籍従業員数 -1年間の離職従業員数)÷ 1年前の在籍従業員数 × 100」
で計算することで、計測期間中に入社した従業員を含めずに定着率を算出できます。例えば、1年前の従業員数が100人で、そのうち1年間の離職従業員数が5名の場合、定着率95%といえます。
定着率の計測期間ですが、1年単位以外にも、新卒採用の社員の定着率を確認する場合には3年単位を用いることが多いですし、5年単位で計測することもあります。
2. 人材が定着しない要因
人材が定着しないということは、離職する人が多いということでもあります。
この章では、どんな要因で離職してしまうのか、人材が定着しない要因にはどんなものがあるのかをご紹介します。
2-1. 人間関係に問題を感じている
人間関係のミスマッチは、年代問わずに発生しています。
人間関係で問題を抱えると大きなストレスを感じたり、モチベーションが低下したり、仕事の効率が下がったりすることも考えられます。
採用段階で会うことができる社員の人数は限られていますし、人間関係でうまくやっていけるかどうかの判断は非常に難しいです。企業側としても、数回の面接で応募者の人物像を見極め、その人物が自社の社員と良い関係性を作っていけるのかまで判断するのは難しいといえます。
2-2. やりがいを感じられない
数値などで目に見える成果が得られること、お客様から感謝されること、仲間から感謝されること、新しいことにチャレンジすること、自分で考えて動くことなど、やりがいを感じるポイントは人それぞれです。
業務内容によって異なるやりがいもあれば、同じ業務であっても会社によってどのようなプロセスを踏むのか、どのような評価をするのかが異なっていれば、やりがいを感じられる人とそうでない人が出てきてしまいます。
業務内容はマッチしていたとしても、企業のスタンスや評価体制が働く人の価値観とマッチしていなければ、やりがいが感じられず離職してしまう可能性が高まるでしょう。
2-3. 評価に不満を感じている
思うような評価が得られないと、ここで働いていても正しく評価してもらえないと感じて転職しようと考える要因になります。
評価制度がしっかりと整備されていなかったり、制度にそった評価がなされていなかったりすることが問題となることが多いですが、評価制度があってもそれを入社時に知らされていなかったり、会社側が求職者がどのような評価を望んでいるのかを理解できなかったりすることも不満を感じる要因となります。
2-4. 労働条件に不満を感じている
労働条件の中でも、特に労働時間や休日に関する条件に不満を感じて離職に至るケースが多いです。残業が多すぎる、休日出勤が多い、代休が取れないなどに対する不満が多いです。
事前に聞いており、理解した上で入社した場合はまだ定着する可能性はありますが、事前の情報と大きく異なるような場合には離職につながりやすいです。
給与面においては、インセンティブの割合が多く想定よりも稼ぐことができなかったり、何らかの要因で基本給やボーナスが減ってしまったり、納得のいかない給与制度に変わってしまうといったことが離職の要因になりえます。
2-5. 勤務地に関する不満がある
勤務地も人材が定着しない理由になることが多いです。
希望の勤務地に配属されないケースは起こり得ると言えますので、ある程度覚悟をして入社する方が多いとは思いますが、実際に希望以外の勤務地で働いてみて、やはり希望の場所で働きたい気持ちが強くなることもあります。
始めは転勤があっても問題ないと感じていても、ライフスタイルなどの変化によって決まった勤務地に定住したいと考えが変わることもあります。
勤務地の希望を叶えられないことや、転勤が多いことは、定着率を下げる要因になることが多いといえます。
2-6. 仕事内容に不満を感じている
特に若手の従業員においては、仕事内容に対する不満が離職の理由に上がることが多いです。仕事内容の不満の中には「希望の仕事ができなかったこと」や「自分の力が活かせないと感じること」や「ノルマが重すぎると感じること」などが挙げられますが、内閣府による就労等に関する若者の意識調査によると「仕事が自分に合わなかった」という理由がもっとも多いとされています。
2-7. 将来のキャリアイメージが沸かない
今、大きな不満はなくても、将来を見据えた時にキャリアイメージが沸かなくなってしまうと、転職しようという考えに至ることがあります。
管理職ポストに空きがなかったり、先輩の話から給与の上昇の見込みがないと感じたり、仕事の広がりがなくスキルを伸ばす機会がないなどが、キャリアアップのイメージが持てなくなる要因として挙げられます。
2-8. 会社の将来性に不安を感じている
業界の先行きが不透明だったり、会社の売り上げが落ち込んでいたり、会社の成長がみられないなどの状況が続けば、その会社で働き続けることに不安を感じるようになります。
給与の未払いが生じたり、最悪の場合は会社が倒産したりといった状況になる前に動こうとする人が増えるでしょう。会社の状態が不安定だと、定着率は下がってしまいます。
3. 定着率が低いことによるデメリット
定着率が低いとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
定着率が低い企業は、何らかの問題を抱えていると見なされ、採用が難しくなる可能性があります。定着率が低いということは離職率が高いことを意味し、離職が続けば人手不足に陥り、採用活動が頻繁になり、その分難易度も上がるため、大きな問題となります。採用の頻度や期間が長くなれば、それだけ費用がかかることにもなってしまいます。教育コストも増大するでしょう。
定着していれば人も育ちますし、人を育てられる人も増えていき、事業成長にも期待できますが、定着しない企業では事業の成長スピードにも影響が出る可能性が考えられます。人員不足の状態においては、業務が回らなくなり、受けられる仕事の量が減って売り上げが下がってしまうことも考えられます。定着率の低さは経営上のリスクにもつながるといえます。
4. 採用段階で導入したい!定着率を高めるための適性検査
定着率が低くなってしまう要因の中でも特に多いといえるのが、採用段階において企業や応募者がお互いのことを理解しきれていなかったことです。採用活動において、本人の特性(性格)や志向を正しく深く理解しておくことが定着率を高めるために非常に重要となります。
そのために採用段階で活用したいのが「適性検査」です。「適性検査」では、短時間で候補者の多くの特性を把握でき、採用判断に役立つ重要な情報を得ることができます。
適性検査には、大きく分けて「能力検査」と「性格検査」があります。
「能力検査」は仕事をする上で必要となる基本的な知的能力を知るための検査であり、「性格(特性)検査」は、その人の性格(特性)を把握するための検査です。
「能力検査」でその人の能力を正しく把握できれば、スムーズに仕事に馴染んで定着することにつながるでしょう。また「性格(特性)検査」の活用は、より定着率を高めることに効果的であるといえます。
「性格(特性)検査」は、ライスケールによって虚偽の回答を検知したり、質問の意図がわかりにくい問題に回答してもらうことで、本来の特性を把握することができるツールです。「積極性」「社交性」「慎重性」「主体性」「決断性」「持久性」「ストレス耐性」など様々な項目の特性を知ることができ、こうした特性を正しく把握することで、自社の企業文化や既存社員との相性、仕事との相性を判断することができます。また、面接での見極めのヒントとなるデータを出力できるタイプの適性検査もあります。こちらを活用すれば、より精度の高い面接を実施することもできるので、ミスマッチの少ない採用を実現できます。このように「適性検査」をうまく活用することで、定着率を高めることができるでしょう。
5. まとめ
定着率を高めるためには、採用時に企業と応募者がお互いのことをよく知り、入社後のミスマッチの防止を強化することが重要です。
「適性検査」を導入すれば、候補者の本来の特性や考えを正しく理解した上で、採用や配属を決めることができますので、定着率を劇的に向上させることに期待できます。「適性検査」は採用担当者のスキルにかかわらず定量的な情報を把握することができる点も、採用手法として優れたポイントです。
適性検査で得られる情報と面接での情報をうまく組み合わせて判断することで、自社にマッチした人を採用して定着率を高めましょう。








